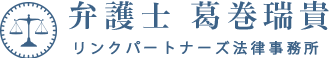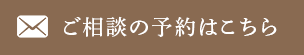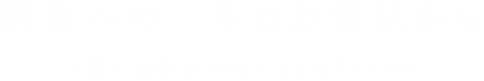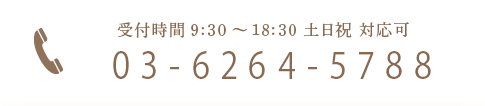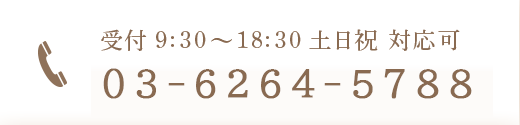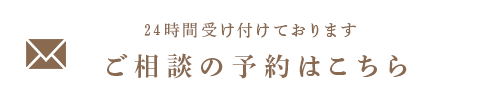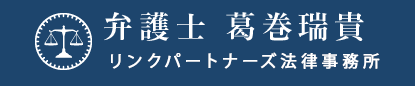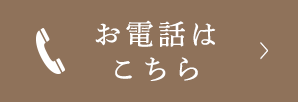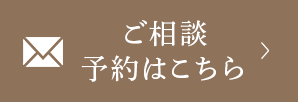皆様、こんにちは。
赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。
今回は、株主名簿の名義書換に関する諸論点を解説していきます。
まずは、会社側が株主名簿の名義書換を正当な理由無く拒絶している場合の法律関係についてです。
1.名義書換の不当拒絶
そもそも、名義書換を行わなければ、会社に対して株主たる地位を主張することができないのが原則です(130条1項)。
しかし、この原則は、会社が不当に名義書換を拒絶している場合も同様に当てはまるのでしょうか。
名義書換制度の趣旨は、株主名簿による株主の集団的・画一的取扱いを可能にする点にあり、会社の利益保護のための規定であるとされています。
そうであるならば、名義書換を不当に拒絶した会社は信義則(民法1条2項)に反し、保護に値しないということができるでしょう。
したがって、名義書換を不当に拒絶された実質上の株主は、名義書換えなくして会社に対して株主であることを主張し得ると解すべきです。
なお、ここでいう不当拒絶には会社の過失による名義書換未了の場合も含まれます。
2.名義書換未了の株主(失念株主)の地位(会社側からの権利行使承認の可否)
(※なお、前提として基準日前の譲渡であることが必要です。)
繰り返しになりますが、名義書換を行わなければ、会社に対して株主たる地位を主張することができません(130条1項)。
では、会社側から、権利行使を認めることができないのでしょうか。
そもそも、名義書換制度の趣旨は、株主名簿による株主の集団的・画一的取扱いを可能にする点にあり、会社の利益保護のための規定です。
そうだとすれば、会社がかかる利益を放棄するのは自由です。
また、条文上も「対抗することができない」とされており、会社の方から権利行使を認めることを禁止しているとは解されません。
したがって、会社が自己の危険において、権利行使を認めることは可能であると解すべきです。
ただし、会社は株主平等原則(109条1項)に配慮しなければならない点に注意が必要です。
すなわち、恣意的な権利行使の承認は許されず、ある名義書換未了の譲受人に権利行使を許容する以上、他の名義書換未了の譲受人全てに権利行使させなければなりません。
(※そうすると、株主数の多い会社では実質株主を把握することは不可能であるから、結局名簿上の株主を一律に株主として扱わざるを得ないことになります。)
3.基準日後の譲渡の場合の株主総会の議決権の行使(124条4項)
ここで、補足ですが、基準日後の株式の譲渡の場合に株主総会の議決権の行使をいかに解するか、という論点があります。
この点も追加で説明しておきましょう。
そもそも、124条4項ただし書の「基準日株主の権利を害する」とは、基準日後に株式を譲り受けた者に議決権を行使するこができるものと会社が定めることにより、当該株式の基準日株主が議決権を行使できなくなるような場合を指します。
これに対し、会社が基準日後に募集株式の発行をし(組織再編行為も含まれる)、新株主に議決権の行使を認める場合には、当該株式についての基準日株主は存在しないから、基準日株主を害することはありません。
もっとも、会社が基準日後に募集株式を発行した場合であっても、株主総会において会社支配権の争奪が生ずることが予想され、取締役会の多数派が第三者割当ての方法によって自派に株式発行を行った上で、会社として議決権の行使を認めることは、違法となる可能性があります。
法律構成としては、124条ただし書に当たり、基準日株主の権利を害すると解する見解や、新株発行の差止めに付随してか、あるいは、既存株主の妨害排除請求権を本案として、議決権行使の差止めが認められると解する見解があります。
4.名義書換未了の株主(失念株主)の地位(譲渡人・譲受人・会社の関係)
⑴会社との関係
名義書換がなされていない以上、会社との関係では依然として譲渡人が株主です(130条1項)。
⑵当事者間の関係
当事者間では意思表示のみで株主の譲渡が可能である以上、株主たる地位は譲受人に移転していることになります。
したがって、譲受人には株式・新株予約権の割当てを受ける権利等や剰余金の配当を受ける正当な権利があります。
そうだとすれば、譲渡人が権利を行使している場合には、それが不当利得(民法703条、704条)となるでしょう。
ここに、増資含みの高値による株式譲渡と株式のプレミアムを取得することは二重の利得となるが、特に後者が不当利得となると考えられます。
では、譲受人は譲渡人に対して何を請求できるのでしょうか。
〈株式の無償割当、分割又は剰余金の配当がなされた場合〉
この場合、譲渡人は何らの経済的出捐をせず、利得していることとなります。
そうだとすれば、配当額や株式そのものが不当利得です。
したがって、剰余金配当であれば配当額を譲受人に交付すべきであるし、株式の無償割当や株式分割であれば、株式そのものを引き渡すべきです。
もっとも、交付すべき株式を既に売却してしまった場合には、価格賠償によるべきであるが、その価格はいかに算定すべきでしょうか。
この点、返還すべき利益を事実審口頭弁論終結時における同種・同等・同量の物の価格相当額と解すると、その物の価格が売却後に下落したり、無価値になったときには、受益者は取得した売却代金の全部または一部の返還を免れることになるが、これは公平の見地に照らして妥当でありません。
逆に、物の価格が売却後に高騰したときには、受益者は現に保持する利益を超える返還義務を負担することになるが、これも同様に当事者間の公平を害することになるでしょう。
そうすると、受益者は、法律上の原因なく利得した代替性のある物を第三者に売却した場合には、損失者に対し売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負うと解すべきです。
〈株主割当てにより募集株式、新株予約権の割当を受ける権利が与えられた場合〉
判例は、この場合譲受人による不当利得返還請求を認めませんが、当事者間では株主たる地位が譲受人に移転している以上、これは対会社との関係と対譲渡人との関係を混同するものであるとの見解が有力です。
そこで、譲受人は、譲渡人に対して不当利得返還請求をなし得ると解するが、株式それ自体は譲渡人自身の支払によって得られたものであるから、「法律上の原因」があり、不当利得とならないでしょう。
よって、原則として価格賠償として、現存利益の限度で不当利得を返還すべき(民法703条)であると解すべきです。
具体的には、引受時の株価と引受価額の差額を上限として、株価が値下がりしている場合は、請求時の株価と引受価額との差額しか請求できないものと解釈されます。
なお、譲受人が払込期日前に、払込金額相当の金銭を提供して、譲渡人に対して請求した場合は、譲受人は譲渡人に対し株式・新株予約権の引渡しを求めることができると解すべきです(民法704条)。
なぜなら、譲受人が株式の引受けの意思表示を行っていた以上、譲渡人が株式を引き受けることができる地位にないからであると説明されています。
以上で、株主名簿の名義書換一般の諸問題を解説いたしました。
株式関係の実務、企業法務(ファイナンス・コンプライアンス)関係のご相談は、弁護士葛巻へお任せください。
ご予約は以下の、予約フォームからお願いいたします。
<<<予約フォーム